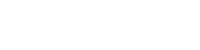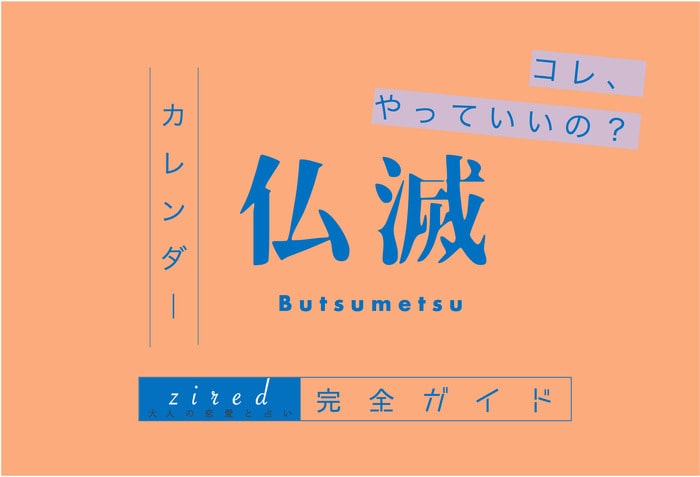

子どもの頃から、身近な大人がこんなことを言う場面に出会ってきた方もいるのでは?
でも、具体的にどんな日なのか?本来の意味まで知っている方は少ないでしょう。
今回はそんな、仏滅について解説。仏滅の本来の意味から、この日にやっていいこと・悪いことまで詳しく解説します。
目次
仏滅とは物がなくなる空しい日
現代では仏滅と書かれるこの凶日、その前は「物滅」と書かれていたそう。もっと前は「虚亡」とも呼ばれていたといいます。
物が形を失い、物事は達成できない、そんなむなしい日という意味が本来の意味です。
そのため「物品の購入を慎む」「何かを始めることを慎む」これが、もともとの意味と思って正解でしょう。
ただ、時代の変遷とともに「物」の部分に「仏」の字があてがわれ、「仏様すらも滅する縁起の悪い日」と呼ばれるようになりました。
「仏様すら滅するなら何をやってもムダ」そんなところから仏滅は、六曜中最大の凶日になったということですね。
なお「仏」という字が入るものの、仏滅が属する六曜は三国時代の中国で生まれたものです。そのため、仏教とも神道とも関係はありません。
仏滅はリセット?縁起が良いとされる考え方も
仏滅の本来の意味は「物が形を失う」。何かがなくなったり、壊れたりする日ということになります。
しかし、この意味をポジティブに変換して、仏滅の日を活用する方もみえるよう。
「物が形を失うならば、今までの物・ことがリセットされる。それによって、すべてを0から始めることができる!」という解釈です。
つまり「仕切り直して、新たなスタートを切る日」として利用できるという考え方ですね。
こじつけと思う方もいるかもしれませんが「病は気から」「イワシの頭も信心から」という言葉もあります。
ポジティブな解釈で気持ちも明るく保てるならば、凶日とされる日も吉日に転換できるでしょう。
また物滅と呼ばれていた時代の仏滅は「物が滅びて新しく始まる日」という、吉日だったという説も。あながち、こじつけとも言い難いポジティブな解釈です。
2025年の仏滅カレンダー
| 仏滅の日付 | 曜日 | 特記 | 重なる吉日(縁起の良い日) | 重なる凶日(縁起の悪い日) |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | 土 | 大明日 母倉日 | ||
| 1月10日 | 金 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 | ||
| 1月16日 | 木 | 受死日 | ||
| 1月22日 | 水 | 一粒万倍日 | ||
| 1月28日 | 火 | 受死日 | ||
| 2月1日 | 土 | |||
| 2月7日 | 金 | 大明日 | ||
| 2月13日 | 木 | 一粒万倍日 天恩日 | ||
| 2月19日 | 水 | 大明日 | ||
| 2月25日 | 火 | 一粒万倍日 天恩日 | ||
| 3月2日 | 日 | 一粒万倍日 大明日 | ||
| 3月8日 | 土 | 母倉日 | ||
| 3月14日 | 金 | 大明日 天恩日 | ||
| 3月20日 | 木 | 春分 | 母倉日 | |
| 3月26日 | 水 | 月徳日 | ||
| 3月30日 | 日 | |||
| 4月5日 | 土 | 大明日 | ||
| 4月11日 | 金 | 大明日 天恩日 | ||
| 4月17日 | 木 | 春の土用 | 大明日 | |
| 4月23日 | 水 | 月徳日 | ||
| 4月28日 | 月 | 一粒万倍日 天恩日 | ||
| 5月4日 | 日 | 大明日 | ||
| 5月10日 | 土 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 天恩日 | ||
| 5月16日 | 金 | |||
| 5月22日 | 木 | 一粒万倍日 母倉日 | ||
| 6月1日 | 日 | |||
| 6月7日 | 土 | 大明日 | ||
| 6月13日 | 金 | 天恩日 | ||
| 6月19日 | 木 | 大明日 | ||
| 6月29日 | 日 | 一粒万倍日 己巳の日 大明日 | ||
| 7月5日 | 土 | |||
| 7月11日 | 金 | 巳の日 母倉日 天恩日 | ||
| 7月17日 | 木 | 大明日 | ||
| 7月23日 | 水 | 巳の日 母倉日 | ||
| 7月29日 | 火 | |||
| 8月4日 | 月 | 巳の日 大明日 母倉日 | ||
| 8月10日 | 日 | 大明日 天恩日 | ||
| 8月16日 | 土 | 巳の日 | ||
| 8月22日 | 金 | |||
| 8月26日 | 火 | 天恩日 | ||
| 9月1日 | 月 | 大明日 | ||
| 9月7日 | 日 | 白露 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 | |
| 9月13日 | 土 | |||
| 9月19日 | 金 | 一粒万倍日 | ||
| 9月24日 | 水 | 一粒万倍日 | ||
| 9月30日 | 火 | 寅の日 大明日 | ||
| 10月6日 | 月 | 天赦日 一粒万倍日 | ||
| 10月12日 | 日 | 寅の日 | 受死日 | |
| 10月18日 | 土 | 大明日 | ||
| 10月22日 | 水 | 天恩日 | ||
| 10月28日 | 火 | 一粒万倍日 大明日 母倉日 | ||
| 11月3日 | 月 | 月徳日 | ||
| 11月9日 | 日 | 大明日 天恩日 | ||
| 11月15日 | 土 | |||
| 11月20日 | 木 | 巳の日 | ||
| 11月26日 | 水 | |||
| 12月2日 | 火 | 巳の日 大明日 | ||
| 12月8日 | 月 | 一粒万倍日 大明日 天恩日 | ||
| 12月14日 | 日 | 巳の日 | ||
| 12月25日 | 木 | 天恩日 | ||
| 12月31日 | 水 |
2024年の仏滅カレンダー(過去アーカイブ)
| 仏滅の日付 | 曜日 | 特記 | 重なる吉日(縁起の良い日) | 重なる凶日(縁起の悪い日) |
|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 金 | 鬼宿日 天恩日 | ||
| 1月15日 | 月 | 寅の日 | ||
| 1月21日 | 日 | 大明日 | ||
| 1月27日 | 土 | 寅の日 月徳日 | ||
| 2月2日 | 金 | 鬼宿日 | ||
| 2月8日 | 木 | 寅の日 大明日 | ||
| 2月13日 | 火 | 大明日 | ||
| 2月19日 | 月 | 雨水 | 一粒万倍日 天恩日 | |
| 2月25日 | 日 | 大明日 | ||
| 3月2日 | 土 | 一粒万倍日 天恩日 | ||
| 3月8日 | 金 | 大明日 | ||
| 3月12日 | 火 | 母倉日 | ||
| 3月18日 | 月 | 巳の日 天恩日 | ||
| 3月24日 | 日 | 大明日 母倉日 | ||
| 3月30日 | 土 | 巳の日 | ||
| 4月5日 | 金 | 受死日 | ||
| 4月10日 | 水 | 大明日 | ||
| 4月16日 | 火 | 春の土用入り | 大明日 天恩日 | |
| 4月22日 | 月 | 大明日 | ||
| 4月28日 | 日 | 月徳日 | ||
| 5月4日 | 土 | 天恩日 | ||
| 5月8日 | 水 | 大明日 | ||
| 5月14日 | 火 | 寅の日 母倉日 | ||
| 5月20日 | 月 | 小満 | 大明日 | |
| 5月26日 | 日 | 寅の日 月徳日 母倉日 | ||
| 6月1日 | 土 | |||
| 6月11日 | 火 | 一粒万倍日 大明日 月徳日 | ||
| 6月17日 | 月 | 天恩日 | 受死日 | |
| 6月23日 | 日 | 一粒万倍日 大明日 | ||
| 6月29日 | 土 | 天恩日 | 受死日 | |
| 7月5日 | 金 | 一粒万倍日 大明日 | ||
| 7月10日 | 水 | |||
| 7月16日 | 火 | 巳の日 母倉日 天恩日 | ||
| 7月22日 | 月 | 大暑 | 大明日 | |
| 7月28日 | 日 | 巳の日 母倉日 | ||
| 8月3日 | 土 | |||
| 8月7日 | 水 | 立秋 | ||
| 8月13日 | 火 | 大明日 天恩日 | ||
| 8月19日 | 月 | |||
| 8月25日 | 日 | 大明日 | ||
| 8月31日 | 土 | 二百十日 | 天恩日 | |
| 9月5日 | 木 | 大明日 月徳日 | ||
| 9月11日 | 水 | 寅の日 | ||
| 9月17日 | 火 | 一粒万倍日 大明日 | ||
| 9月23日 | 月 | 寅の日 月徳日 | ||
| 9月29日 | 日 | 一粒万倍日 | ||
| 10月4日 | 金 | 母倉日 | ||
| 10月10日 | 木 | 大明日 | ||
| 10月16日 | 水 | 天恩日 | ||
| 10月22日 | 火 | 大明日 | ||
| 10月28日 | 月 | 天恩日 | ||
| 11月1日 | 金 | 己巳の日 大明日 母倉日 | ||
| 11月7日 | 木 | 立冬 | ||
| 11月13日 | 水 | 巳の日 天恩日 | ||
| 11月19日 | 火 | 大明日 | ||
| 11月25日 | 月 | 巳の日 | ||
| 12月6日 | 金 | 鬼宿日 大明日 月徳日 | ||
| 12月12日 | 木 | 大明日 天恩日 | ||
| 12月18日 | 水 | 大明日 | ||
| 12月24日 | 火 | 月徳日 | ||
| 12月30日 | 月 | 天恩日 |
仏滅にやっていいこと悪いこと
ここからは、仏滅にやっていいことと悪いことを表形式で解説しましょう。
なお、×のついた行動でもポジティブな解釈ができたり、周りの同意を得られるものであれば、〇に転換できる可能性もあります。
解説も参考にしつつ、周りの人と話し合って、行動に移すかどうかを決めましょう。
| 行動 | やっていい度 | 解説 |
|---|---|---|
| 結婚式 | × | 縁起の悪い日に慶事を行うことは、凶運を慶事に呼び込むこととして嫌われる。また結婚式は、新生活を始める節目の式なので、物事を始めることにあたる。仏滅に行うと「新生活が成り立たない」という意味になりうる。 一方、式が安くできる可能性もある。仏滅をポジティブに解釈でき、関係者の同意が得られれば行うことも可。 |
| 葬式 | 〇 | 仏滅は弔事には差し支えのない日とされる。むしろ、「友を黄泉の世界に招いてしまう」とされ、友引こそが忌み嫌われる日。仏滅の日に行っても問題はない。 また、本来仏教や神道と六曜が関係ないことからも、避ける必要はない。 ただし、暦を重んじる方が身近にいる場合は注意。仏滅は何をしてもダメと思っている可能性がある。 |
| 納車 | × | 車は「大きな物」。物が滅する日が仏滅なので、事故やトラブルで早々に車を失うことになりかねない日と解釈できるため、避けたいもの。 また、新たな車を迎え入れるという慶事が、縁起の悪い日にふさわしくないとも考えられる。 この日の納車を避けられなければ、神社等でお祓いを受けたり、お守りを頂くと安心材料にできる。 |
| 法事 | 〇 | 弔事は仏滅に行っても問題がないとされる。葬儀同様、回忌法要等も行って問題はない。 また、仏教や神道と六曜にかかわりはないため、仏滅に法事・祭儀を依頼しても断られることはないはず。仏滅にこだわりすぎず、縁者が集まりやすい日を選んで。 ただし、身近に暦を重んじる方がいる場合は、気にするかもしれないので注意を。 |
| 引っ越し | × | 基本的に引っ越しは慶事なので、凶日には避けるべきこととされる。また引っ越しは、新生活を始める日なので仏滅に避けるべき、物事を始めることにも該当する。 ポジティブに解釈することもできるが、周囲や近所の人が暦を重んじる場合もあるので注意が必要。特にマイホームへの入居・新婚生活の開始は避けるべきとの声もある。 |
| お宮参り | △ | 本来、神道と六曜に関係はないので気にする必要はない。仏滅だからとお宮参りに限らず、参拝全般を避ける必要はないとの声もある。 ただし祖父母等が六曜を気にする場合はクレームがつくこともありうる。周りとよく話し合って日取りを決めるのが重要。 逆にそういった方もいることで、神社が混雑しづらいというメリットはある。 |
| 七五三 | △ | 基本的な考え方は、お宮参りと同じ。関係がないので気にする必要はない。神社側が、仏滅だから七五三の祈願をしないということはまずないはず。神社の前に掲示されたり、広報等で案内の来る、祈願の日を利用すれば安心。 ただし、暦を気にする方が身近にいる場合は、慶事を凶日に行うことに難色を示される場合もあるので注意。 |
| 初詣 | △ | 仏教・神道どちらとも六曜とは関係ない。そのため、初詣の日と仏滅の日が重なっても問題なく参拝できる。 ただし、同伴者が暦を気にする場合は配慮を。また、どうしても自分が仏滅を気にしてしまうという場合も回避した方が気持ちは安定するはず。 午後からは運が回復するという説もあるため、こちらを採用するのも1つの方法。 |
| 入籍 | × | 入籍は新たな家庭を作る日。仏滅の日に避けるべきとされる、新しいことを始めることに該当するため、避けたい。また、凶日に慶事を避けるべきという考え方にも該当する。 ただし、仏滅の意味をポジティブに捉えることができ、周りの人を説得できるならばこの日の入籍も可能。大安よりも窓口が混雑しづらいというメリットも。 |
| 宝くじ購入 | × | 運任せの宝くじ当選を目指す行動は、購入や保管方法にもゲンを担ぎたいもの。凶日は可能な限り避けて吉日に行うことがおすすめの行動。 また、買い物は「物が滅する・失う」とされる、仏滅の日には避けることともされる。 さらに凶日の持つ凶運が影響を及ぼすので、吉日が重なっている日でも購入は避けるべきという声もある。 |
| お通夜 | 〇 | 弔事を行うことには問題のない日なので、葬儀と同様にお通夜も行っても問題はない。また、六曜は仏教や神道と関係ないものなので、本質的に気にする必要はないとされる。気にせず行ってOK。 ただし、仏滅には何をやってもダメと思っている方がいる場合には、説明や配慮が必要。参列者の中にも気にする方がいる可能性もある。 |
| 厄払い | 〇 | 仏教・神道と六曜は関係ないため、この日だからと厄払いの祈祷を断られる可能性はまずない。むしろ、これまでの厄を払って吉運を迎え入れる日、新たなスタートを切る日として利用可能。厄払い以外の参拝・祈祷にも利用できる。 仏滅しか日程が融通できないが、仏滅が気になる場合は、午後に祈祷の時間を確保するのがおすすめ。 |
| お墓参り | 〇 | 物事を始めることでも、慶事でもないので仏滅の日に行っても全く問題はない。また、仏教や神道とも関係ないことなので、お寺や神社等からクレームがつくこともまず考えられない。 ただし、同行者の中に暦を気にし、仏滅にはお参りしたくないという方がいるかもしれない。1人で行くならば問題ないが、周りの人への配慮は必要。 |
仏滅に関する気になる疑問


仏滅の基本がわかっても、意外と「こんな時はどうするの?」と迷ってしまうことは多いもの。
ここからは知って損はない、仏滅に関する気になる疑問にお答えしましょう。
一粒万倍日と仏滅が重なるときの考え方
2つの説があります。1つ目は一粒万倍日が仏滅の凶の作用を半分抑えてくれるという説。2つ目は仏滅と吉日が重なった場合、仏滅が吉日の作用を損ねてしまうという説です。
いずれにせよ、一粒万倍日本来の吉運は発揮しづらくなる日といえるでしょう。
そのため、一粒万倍日として活用することは避けておいた方が無難。
宝くじを買ったり、福財布を買ったりといった金運アップの行動は、仏滅と重ならない日にするのがおすすめなのです。不要な買い物、大きな買い物も避けておきましょう。
その他、貯金を始めたり、口座を開設する、新しいことを始めるといったことも避けて正解です。
いずれも、仏滅の日に避けるべき「新しいことを始める」「買い物を避ける」に該当します。
仏滅だけど午後から大安?
これは、六曜の並びに由来した考え方です。六曜は一部例外があるものの、「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の順で巡ります。つまり、仏滅の後には大安がやってくるのです。
ところで、四柱推命や九星等、東洋由来の占いで、バイオリズムのグラフを見たことのある方も多いでしょう。
運勢がどん底から、絶好調の時期に上昇する時を思い出してください。
グラフはまあまあの運気を短期間なりとも推移してから、絶好調に達してはいないでしょうか?
仏滅から大安の日への運気の移り変わりもこれと同様で、仏滅の日でも午後になれば大安に向けて、運気が上昇していくとされます。
そのため、仏滅の日は午後に限ってですが、大安に足を突っ込んだ運の良い日とされるのです。